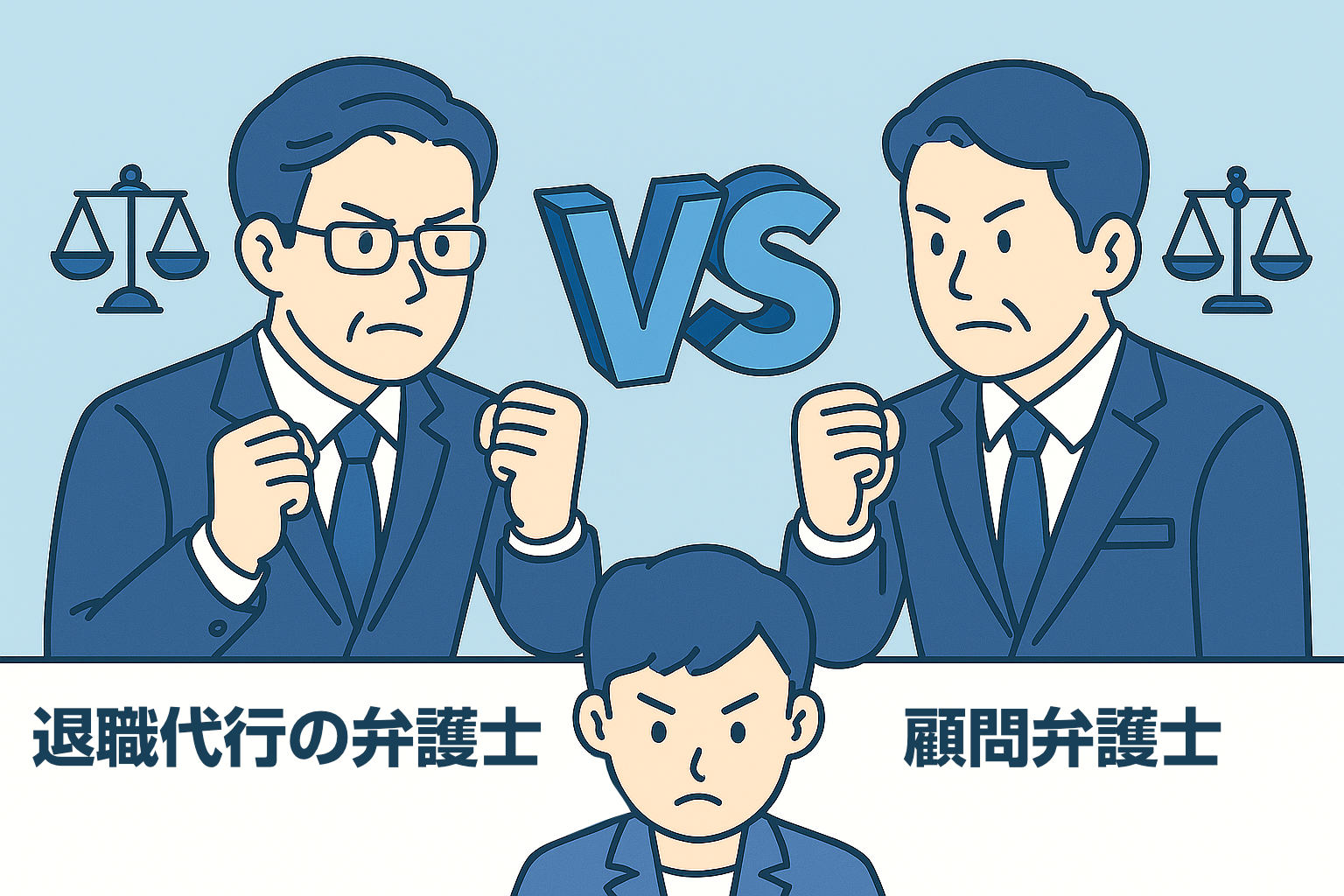🤝顧問弁護士がつく企業への「弁護士による」退職代行戦略:徹底解説
顧問弁護士がいる会社の退職代行。
企業に顧問弁護士がついている場合、通常の退職代行業者(非弁護士)では対応が困難になるケースが想定されます。それは、会社側が顧問弁護士を通して「交渉権のない業者」とのやり取りを拒否したり、法的な対抗措置を検討したりする可能性が高まるためです。
このような状況で、依頼者(従業員)が円滑かつ法的に確実に退職を成立させるためには、「弁護士」に退職代行を依頼することが必須の戦略となります。
顧問弁護士がいる会社で弁護士が必須となる理由
法的交渉権の独占(非弁行為の回避)
非弁護士の退職代行業者が会社と「交渉」を行うことは、弁護士法第72条に違反する「非弁行為」にあたります。
- 一般の代行業者: 従業員の「使者」として退職の意思を伝えることしかできません。
- 顧問弁護士の対応: 会社側の弁護士は、この法的権限の制約を熟知しており、非弁護士の代行業者に対しては「交渉には応じない」「本人の意思を書面で確認する」などの対応を取ることが可能です。最悪の場合、代行業者を非弁行為として問題視する動きに出るリスクもあります。
- 弁護士の退職代行: 弁護士は法律により、退職日、有給消化、未払い賃金、退職金など、退職に伴う一切の事項について代理人として会社と交渉する権限を持ちます。会社側の顧問弁護士に対しても、対等な立場で法的議論が可能です。
会社側弁護士の関与を想定した「備え」
会社に顧問弁護士がいるということは、会社側も法的なリスク管理を重視している証拠です。
- リスク対応力: 会社側が損害賠償請求や業務妨害などを主張してきた場合、非弁護士の代行業者では一切の法的対応ができません。弁護士であれば、これらの法的トラブルに即座に対応し、依頼者の防御を行うことができます。
- 信頼性・確実性: 会社側の顧問弁護士は、相手が弁護士であれば、「法的な手続きを踏めば退職は不可避である」ことを認識しており、無用なトラブルを避けて手続きを進める可能性が高まります。
弁護士による退職代行の具体的戦略(ステップ)
会社側の顧問弁護士の存在を前提とした、弁護士ならではの戦略的アプローチを解説します。
ステップ1: 詳細なヒアリングと法的論点の整理
単に退職の意思を伝えるだけでなく、以下の法的な論点を洗い出します。
- 潜在的な請求権の有無: 未払い残業代、ハラスメントによる慰謝料請求の可能性、不当な労働環境の有無。
- 退職日の確定: 民法627条(期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間で終了)を盾に、会社側の顧問弁護士に対して法的根拠をもって退職日を主張する準備。
- 有給休暇の確認: 残りの有給消化の意思を確認し、退職日までの間に消化することを強く求める法的戦略を立てます。
ステップ2: 会社(顧問弁護士)への通知と交渉開始
弁護士が会社の顧問弁護士宛、または会社代表者宛に「受任通知書」と「退職通知書」を送付します。
- 通知内容の戦略性: 通知書には、単なる退職の意思だけでなく、弁護士が代理人として交渉する権利を有すること、および未払い賃金や有給消化など依頼者の要求事項を明記します。これにより、会社側の顧問弁護士に対して、交渉の必要性を認識させます。
- 法的圧力の利用: 会社側が退職を拒否したり、引き継ぎを強要したりした場合、弁護士は即座に法的な手続き(労働審判、訴訟など)の可能性を示唆することで、顧問弁護士に「穏当な解決」を促す圧力をかけることができます。
ステップ3: 顧問弁護士との交渉フェーズ
会社側の顧問弁護士が窓口になった場合の交渉におけるポイントです。
- 対等な交渉: 弁護士同士の交渉となるため、感情論ではなく、労働法と判例に基づいた論理的な議論が展開されます。
- 書面主義の徹底: 電話でのやり取りを避け、交渉内容をメールや書面(FAX、内容証明など)で記録に残すよう徹底します。これは、後にトラブルになった際の確固たる証拠となります。
- 要求の包括的な解決: 退職日だけでなく、以下の事項についても包括的な合意を目指します。
- 離職票・源泉徴収票などの書類の送付時期
- 未払い賃金・退職金の支払い時期
- 会社貸与品の返却方法(郵送など、依頼者が会社に行く必要がない方法)
ステップ4: 労働審判・訴訟への移行(最終手段)
会社側の顧問弁護士が不当に退職を妨害するなど、交渉が難航した場合でも、弁護士は以下の手続きを代行できます。
- 労働審判: 裁判所を通じた迅速な紛争解決手続き。会社側の顧問弁護士も無視できない公的な場での手続きです。
- 訴訟: 会社が損害賠償請求などの法的措置を講じた場合、弁護士は依頼者の代理人として、その訴訟に対応し、依頼者の権利を守ります。
弁護士に依頼する際のチェックポイント
顧問弁護士がつく会社を相手にする場合、退職代行を依頼する弁護士選びも重要です。
| チェックポイント | 理由 |
| 労働問題の経験 | 単なる一般民事ではなく、労働法規に関する深い知識と交渉経験が必須。 |
| 費用の確認 | 基本料金、交渉費用、労働審判・訴訟へ移行した場合の追加費用を明確にする。 |
| 面談・相談の有無 | 弁護士本人と直接コミュニケーションを取り、戦略や方針を共有できるか。 |
| レスポンスの速さ | 即日対応など、依頼者の不安を取り除く迅速なフットワークがあるか。 |
結論:顧問弁護士がいるなら、安心を「買う」
企業に顧問弁護士がついている状況は、従業員にとって「法的な壁」が立ちはだかっている状態といえます。
この壁を乗り越え、円滑かつ確実に、そして一切の交渉リスクから解放されて退職を完了させるためには、法的交渉のプロフェッショナルである「弁護士」に依頼することが、最も安心で確実な唯一の戦略です。
弁護士費用は発生しますが、これは法的トラブルから完全に解放されるための「安心料」であり、顧問弁護士を相手にする場合は最も費用対効果が高い投資と言えるでしょう。